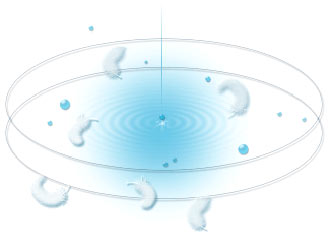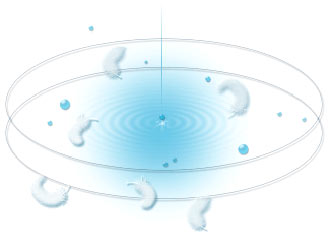悪夢到来!!! スミスさん家の事情3
時を坂のぼること2時間前。
「ふんふふんふーーんふふふふんんんんんんんぅぅぅぅっっ」
豪奢な一室に実に楽しげな鼻歌が聞こえた。
お世辞にも上手いとは言えなかったが本人がとても楽しい気分なのはよく分かった。
「へっへーーあいつら驚くだろうなー」
シュッと慣れない手つきでネクタイを結ぶ。
鏡の中には自分自身見慣れないカッチリとした紳士が立っている。
「う゛〜ん・・似合ってんだか似合ってねーんだか・・・」
それすらも解らんと呟く。
あまり機能性を重視していないと思われるタキシードをビシリと着込むと窮屈で仕方がない。
ネクタイを何度も直し満足したのかよしっと一つ頷く。
「あらお父様準備バッチリですわね」
背後で開いた大きな扉から可愛い娘がひょっこり顔だけをだした。
親ばかとかそう言うのではなく、本当に可愛らしい顔立ちの娘は今はまだ幼いからいいが、あと数年すれば近寄ってくる虫どもがうじゃうじゃ湧いて出るだろうと父は不安で堪らない。
「まあな。お前も早く着替えておけよ。・・・っておいっ」
声に反応するように振り返ってみるとすでに準備完了した娘が目に入り、ついつっこんでしまった。
「お父様と一緒でわたくしも拗ねてますのよ。ひどいですわよね仲間はずれなんて」
フリルをふんだんに使った赤いドレスに白い靴下。
赤い靴は先が丸まっていて愛らしい。
栗色のサラサラの髪を彩るリボンは黒いシルク地のものだった。
一見して金持ちの令嬢だ。
別に拗ねてるわけでは・・と口の中でもごもご言いつつ、
「我が娘ながら可愛いぞ」
お世辞じゃなく呟いた。
「ありがとお父様。でもお父様の方が普段とのギャップで3割り増し素敵に見えますわ」
(誉められてんのか貶されてんのかわかんねーぞ)
「いつもそーゆー格好なさればいいのに」
「冗談っこんなちっこい箱にむりやりギュウギュウ詰めにされたような状態こんな時でもなきゃやんねーよ」
「っちぇーーー」
唇をとがらす娘に肩をすくめる。
あごを触るとつるりと指が滑った。
(・・・ひげがねーのって何年ぶりだか・・)
違和感がぬぐえないが背に腹はかえられないのだ。
「あと一時間ありますわね。わたくしお母様に可愛いバックを見立ててもらってきますわ。」
お母様の趣味って私好みですのよねーと楽しげに背を向ける娘に微笑みながら男は近くのタンスから帽子とマフラーとコートを選び出した。
どれも洗礼された仕立てで、一般庶民にはとうてい手に出来ないほどの物だった。
簡単に言えばこの男大金持ちだということだ。
そんなに高価な物をボンボンっと近くのソファに放り投げると準備終わりとばかりにその向かいの一人掛けソファにドサッと座り込んだ。
そして机に置いてある鈴を一振りすると執事がやってくる。
「お呼びでございましょうか旦那様」
「これ玄関に運んどいてくれ。それと茶ぁ一杯」
「かしこまりました」
そんな主を内心どう思ったか定かではないが執事は無表情で優雅に頭を下げた。
足を組み、おおざっぱな動作でティーカップを傾けるその姿は意外に優美だった。
言葉遣いこそ乱暴なものの、こういう紳士的な動きもやれば出来るのだ。
ついでに言えばかなりの美男子である。
30代の半ばだろうが、目は輝き若々しさを感じさせる。
この口調がなければこの人がだれか、館の住人従者達は永遠に解らないだろう変貌だった。
「うーん実に楽しみだ」
そんな彼はただ自分のいたずらが成功をおさめる事しか頭にないのか始終綺麗な顔をにやつかせていた。
「お母様どの鞄がいいかしら?」
「そうねぇ。その格好ならーこれかしら?でもこれもいいわねぇ」
手持ちと横かけで悩む。
「ですわよね。この二つでわたくしも悩んでましたの。さすがお母様ですわ」
「ところであの人の準備はすんだのかしら?」
「ええ。お父様でしたら今頃のんびりとティータイムですわ」
「手伝うって言ったのに追い出すんですもの。つまんないわー」
「お母様が以前調子に乗りすぎたツケですわね」
また着せ替え人形にされてはたまらないと思ったらしい。
「だあってぇぇ。あの人ったらあーゆー格好似合うのにめったに着てくれないんですものぉ〜」
だからと言って二時間も着せ替えごっこをされてはたまらない。
「今回だって絶対に行かないって言ってたパーティーに突然参加するしぃー」
「あーゆー人間関係がゴチャゴチャしているところお父様嫌いですものねー」
「そーよー。そーゆーのには参加しないって言ったのにたかだか友人にのけものにされて悔しいからってそれだけの理由でその言葉覆してしまうんですものねぇ」
緩すぎる決意だことと辛辣に述べるこの母。
娘同様白い肌に栗色の巻き毛未だ20代でとおる美人妻だが、おっとりした口調とは裏腹に意外に口調にとげがあった。
いつもと同じ柔らかい口調だから余計に怖い。
「お・・お母様・・なんでご存じなのかしら・・」
「まあ。情報と言うのはいつでも大切なものよね?それが大切な旦那様や可愛い娘の事ならなおさらよ」
「・・・・」
ようするに調べたのだろう
(さすがお母様。)
侮れない母に背筋を冷やす。
「危険だからついていくのだめっていうのはわかるわよ?でもなんで私だけだめなのぉー」
「そ・・それはお母様が・・その・・・なんというか・・・」
運動音痴・・・とズバリ口に出来ないのが痛い所だ。
「あ・・ああっ解りましたわっっ。お父様きっとご友人にお母様を紹介するのが照れくさいんですわ」
とりあえず母を納得する為の言い訳だったが次第にそれが真実のような気がしてきた。
「まあ・・あの人ったら相変わらずの照れ屋さんなのねぇ」
一気に機嫌の直った母がフフ・・と頬に手をあて嬉しげに笑った。
そして話題転換とばかりに発せられた第一声はこれだった。
「そうそう。あの小さな子と探偵さんって本当にそういう仲なのかしら?」
ワクワクと期待に満ちた顔で尋ねられて娘は顔を輝かせた
「まあっお母様も興味おありなのね」
そして話題に花開き父が呼びにくるその時まで延々その話で持ちきりだった。
親子である。
見事に遺伝子を分け合った親子であるそれを感じさせる二人だった。
小説部屋 Next
|